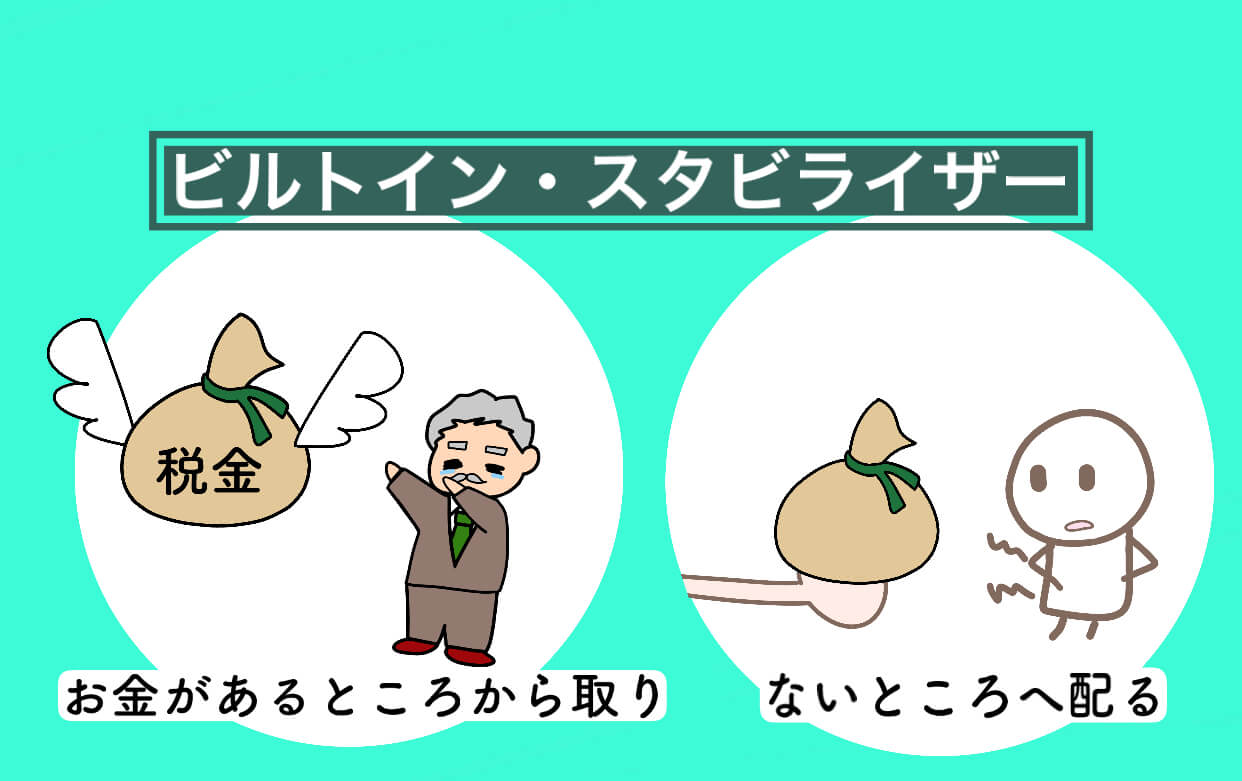「裁量的財政政策」と「伸縮的財政政策」は、よく同じ意味で使われますが、意味に違いはあるのでしょうか?
私が考えたことを、書いてみます。
結論からいうと、私の感想としては、「同じ意味で使うことが多い」と思います。
共通点
まず、「裁量的財政政策」と「伸縮的財政政策」の共通点についてです。
どちらも、景気を調節する政策という意味で使われます。
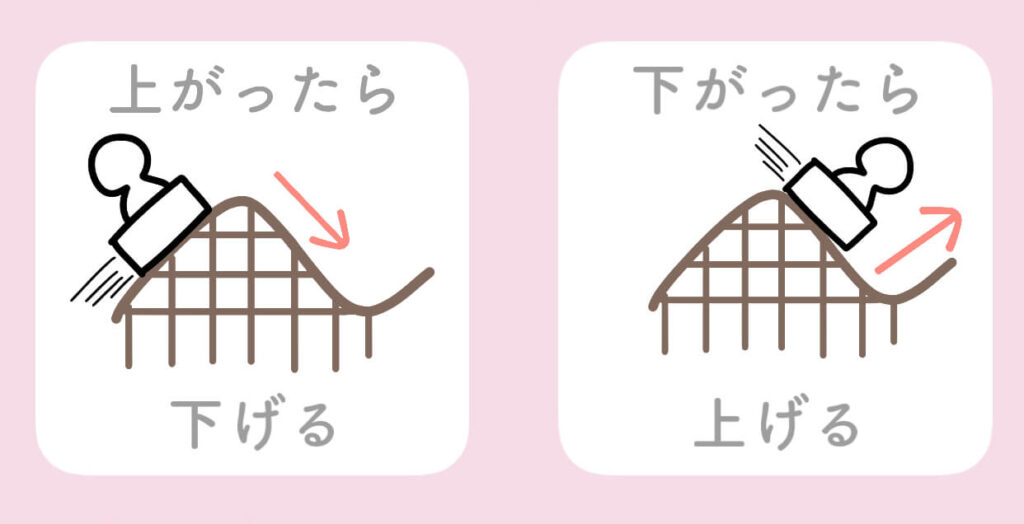
単語の意味
次に、「裁量的」と「伸縮」のそれぞれの意味や、具体的な使い方についてみてみます。
裁量的
裁量とは、その人自身の考えに基づき、物事を判断し決定することです。
例えば、「あなたの裁量に任せます」という言葉は、「あなたが自由に決めてください」という意味です。
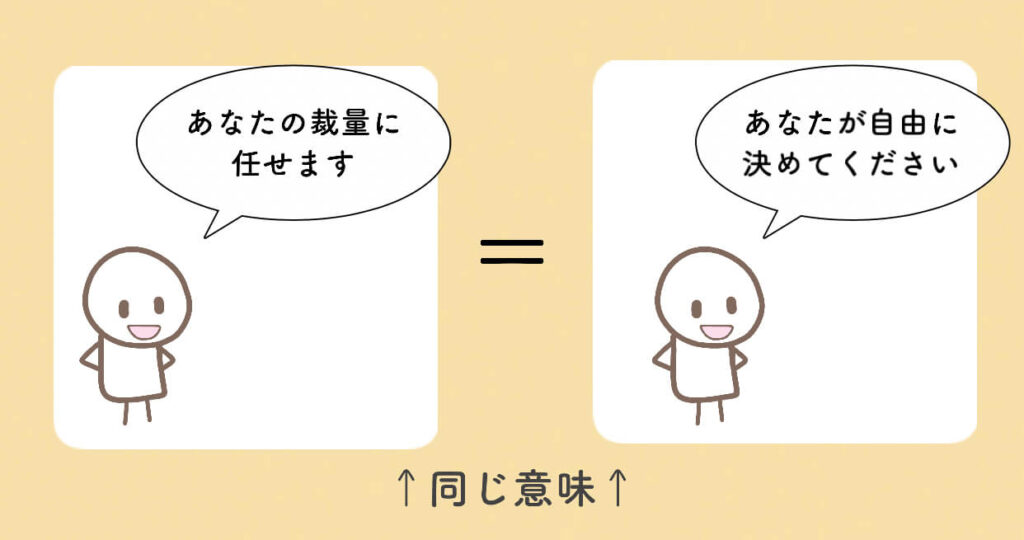
また、経済学では、「裁量」と「ルール」を対義語のように使います。
裁量があるというのは、ルールに従うのではなくて、自分の頭で考えて判断をする状態です。
例えば、食堂のおばちゃんが、裁量的であれば、おばちゃんの気分によって、定食の量が変わるかもしれません。
しかし、お茶碗1杯=○gなどのルールがしっかり決まっていれば、いつでも定食の量は同じです。
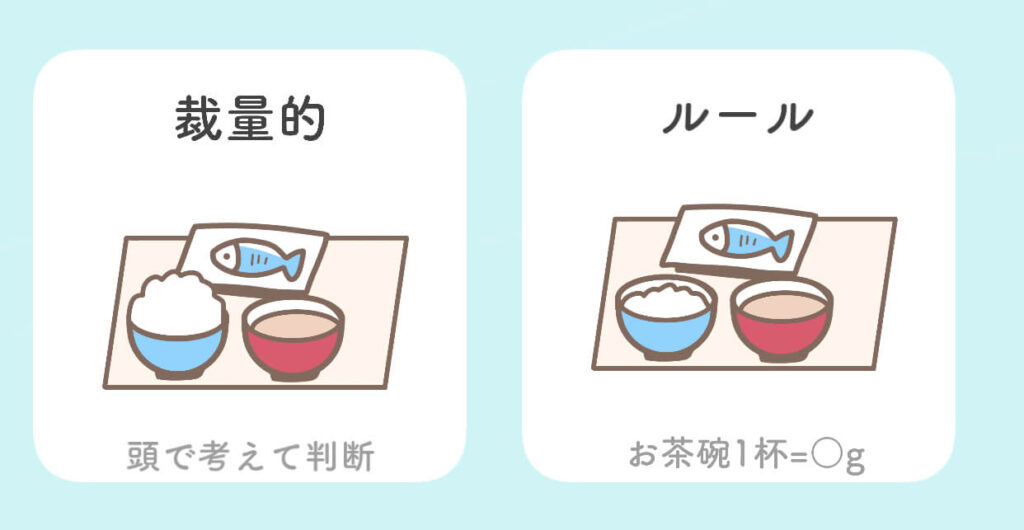
経済学では、誰が裁量権を持ってるのでしょうか?
それは、政府で働いている人です。
政府で働いている人が、景気を見て、政策を決めています。
そのため、政府の人が裁量権を持っています。
政府の人が、臨機応変に、その都度考えていこう、という考え方です。
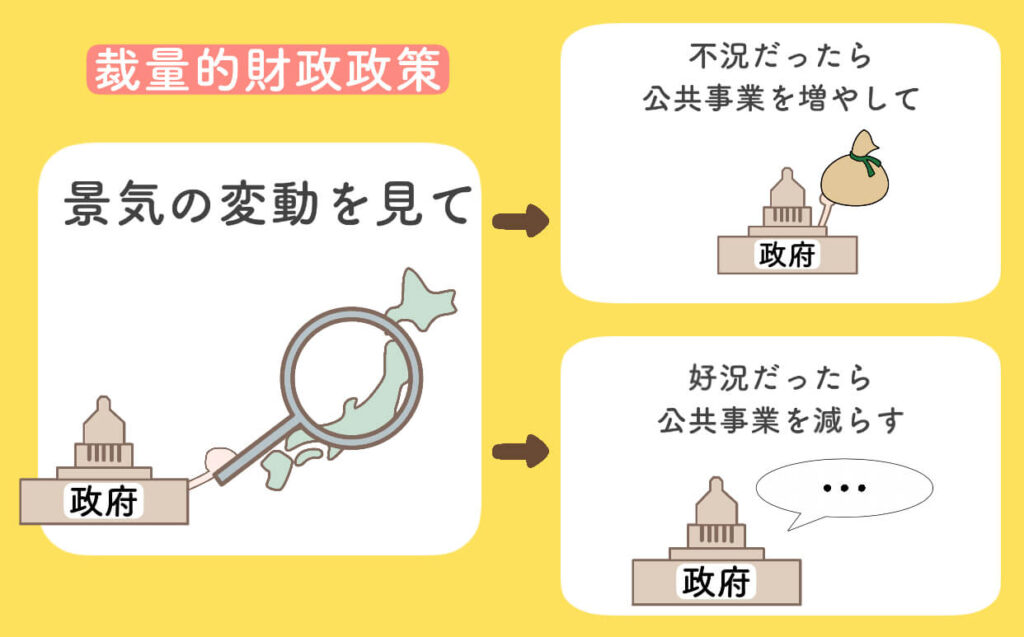
景気が良くなると、みんなの給料が増えます。
その時は、税金を増やして、みんなの給料がちょっと減るようにします。
また、景気が悪くなると、みんなの給料が減ります。
その時は、公共事業をして、みんなの給料が増えるようにします。
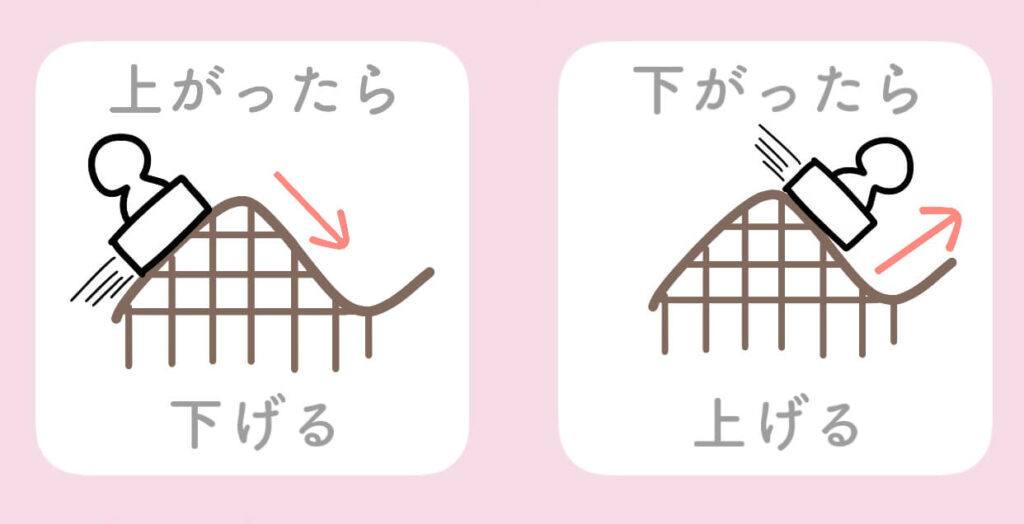
伸縮
次に「伸縮」についてです。
伸縮の意味は、伸びたり縮んだりするということです。
・この生地は伸縮性がある
・この枕は伸縮性がある
生地は、引っ張って伸ばそうとすると、逆に縮まろうとするチカラが働きます。
また、枕は、ギュッと小さくしようとすると、逆に大きくなろうとするチカラが働きます。
つまり、伸縮性があるものは「もとに戻ろうとするチカラ」があるのです。
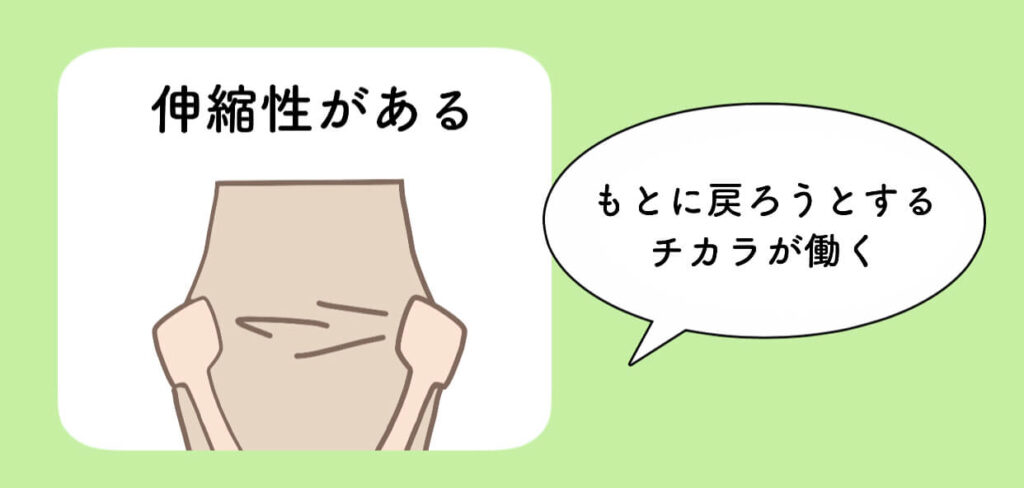
それでは、経済学では、何が「伸縮」してるのでしょうか?
答えは、価格です。
値段は、上がりすぎると下がります。
そして、下がりすぎると上がります。
メルカリで、モノを売ったら、人気なら、高くても売れるかもしれません。
高くても売れそうな時は、商品の値段を高くします。
しかし、値段が高すぎると、売れなくなります。
売れなかったら、値段を低くします。
このように、値段が低すぎたら、高くして、高すぎたら、低くするのです。
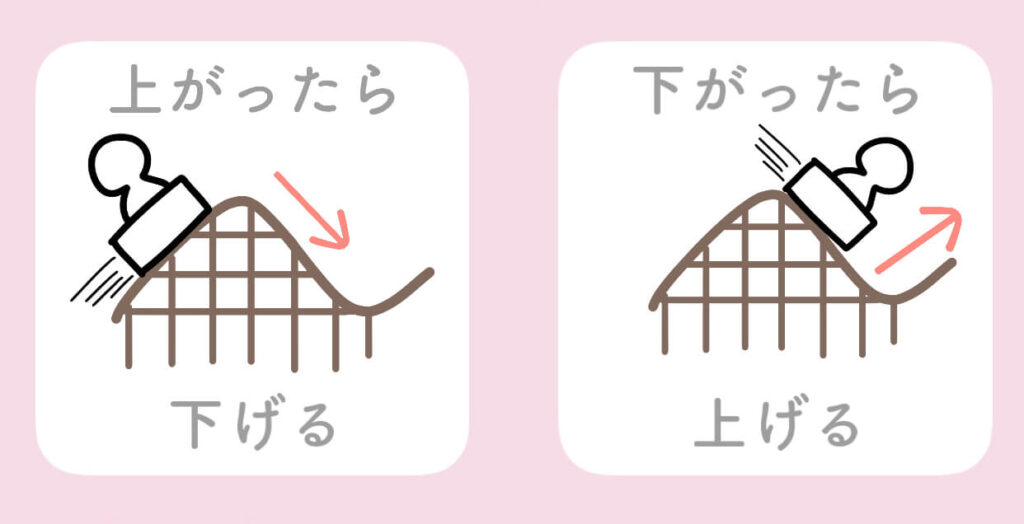
価格が上がったり下がったりする時、「価格は伸縮的である」と表現します。
逆に、価格が上がったり下がったりしない時「値段が硬直的である」と表現します。
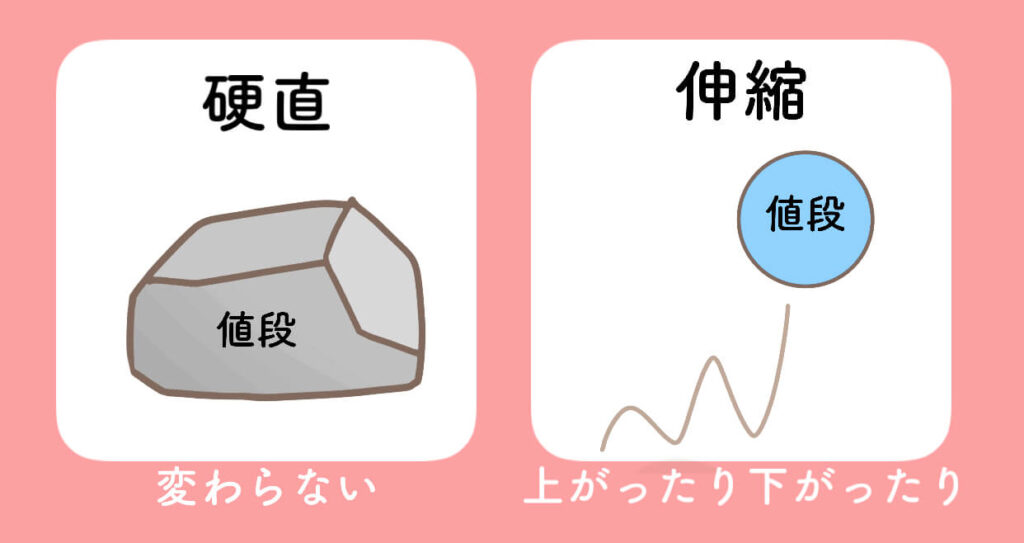
景気が良い時は、商品の値段が上がります。
そのため、景気が良い時は、税金をたくさんとります。
そして、景気が悪い時は、商品の値段は安くなります。
景気が悪くなったら、税金を減らします。
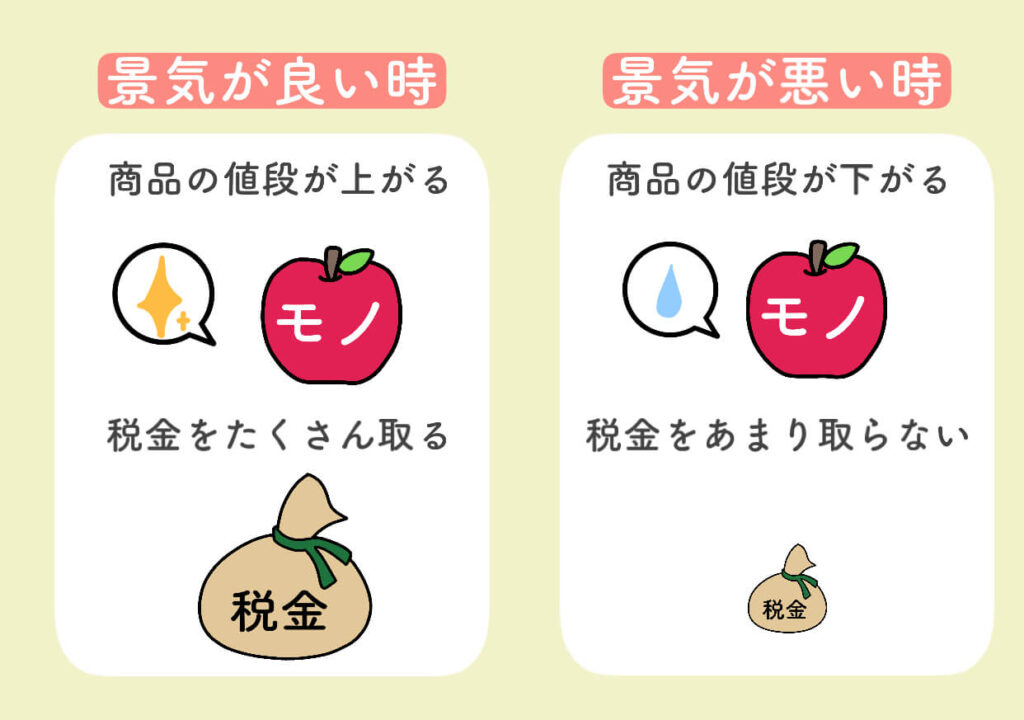
経済学での意味
それでは、経済学でいう「裁量的財政政策」と「伸縮的財政政策」は、どのような違いがあるのでしょうか?
私の意見では、この2つは、同じ意味で使われることが多いと思います。
なぜなら「裁量的財政政策」と「伸縮的財政政策」を、同じ意味として紹介してるサイトが多くあるからです。
どちらも、「ルール」の対義語として、使われています。
なので、同じ意味として捉えても、問題ないのではないかな、と考えています。