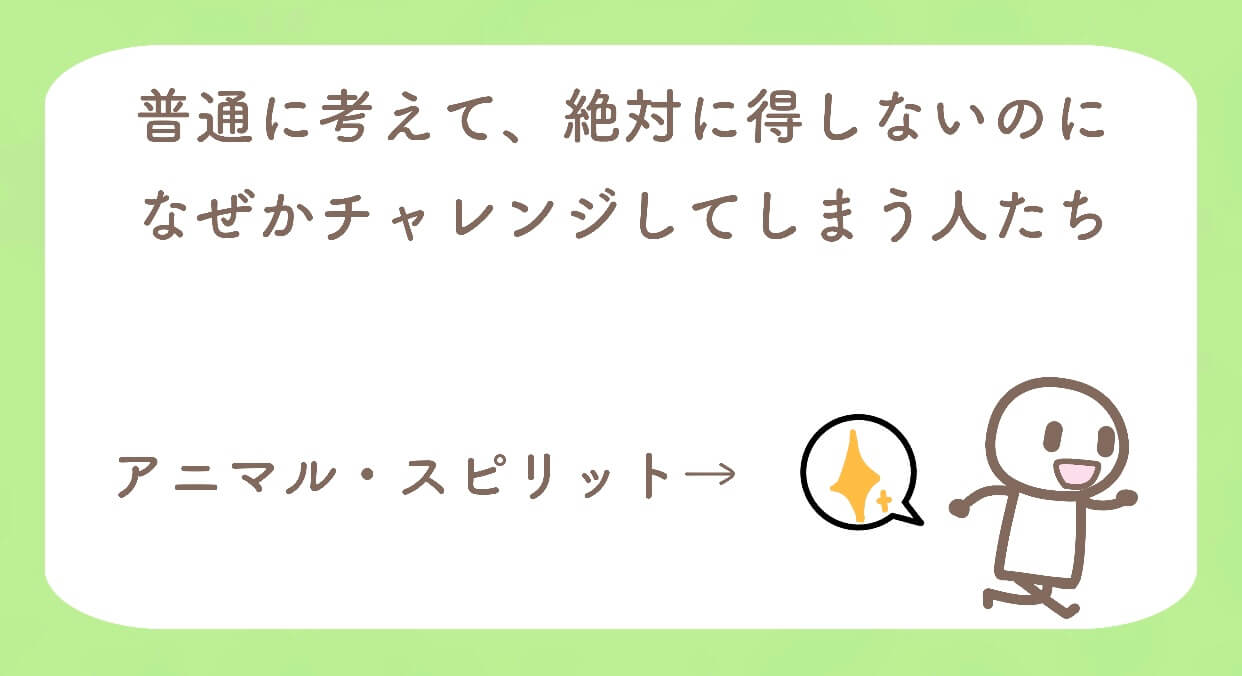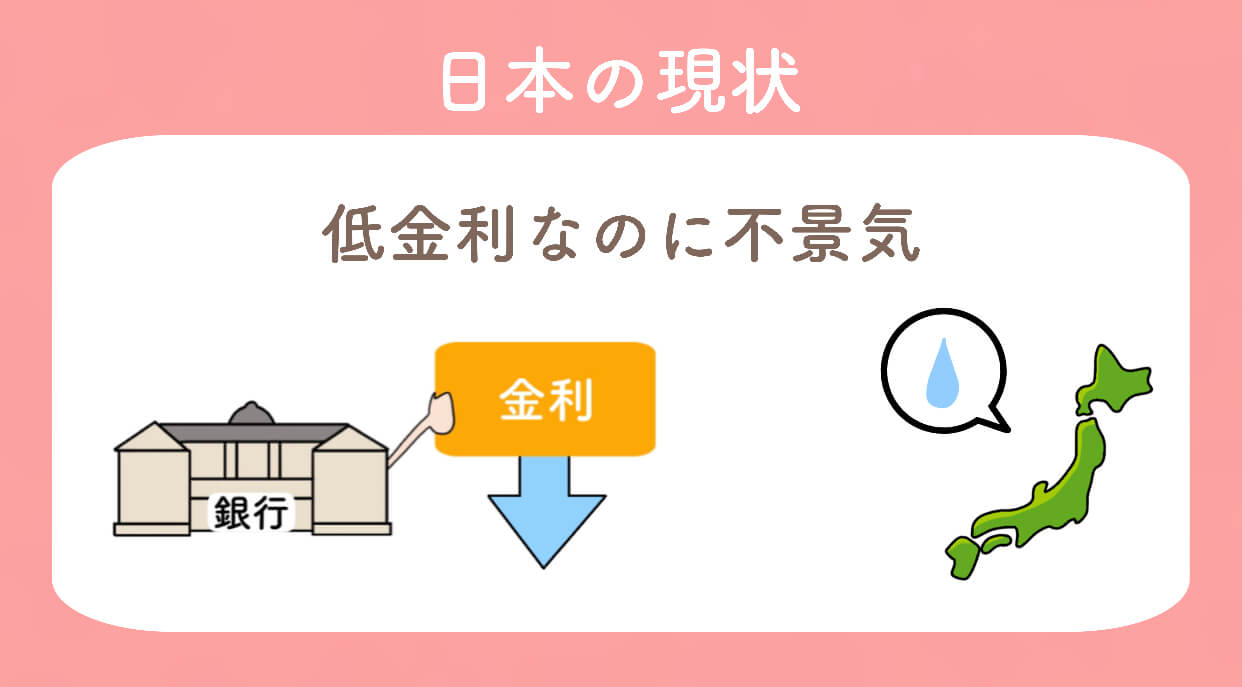ケインズより、前の時代を生きた人たちのことを「古典派」と言います。
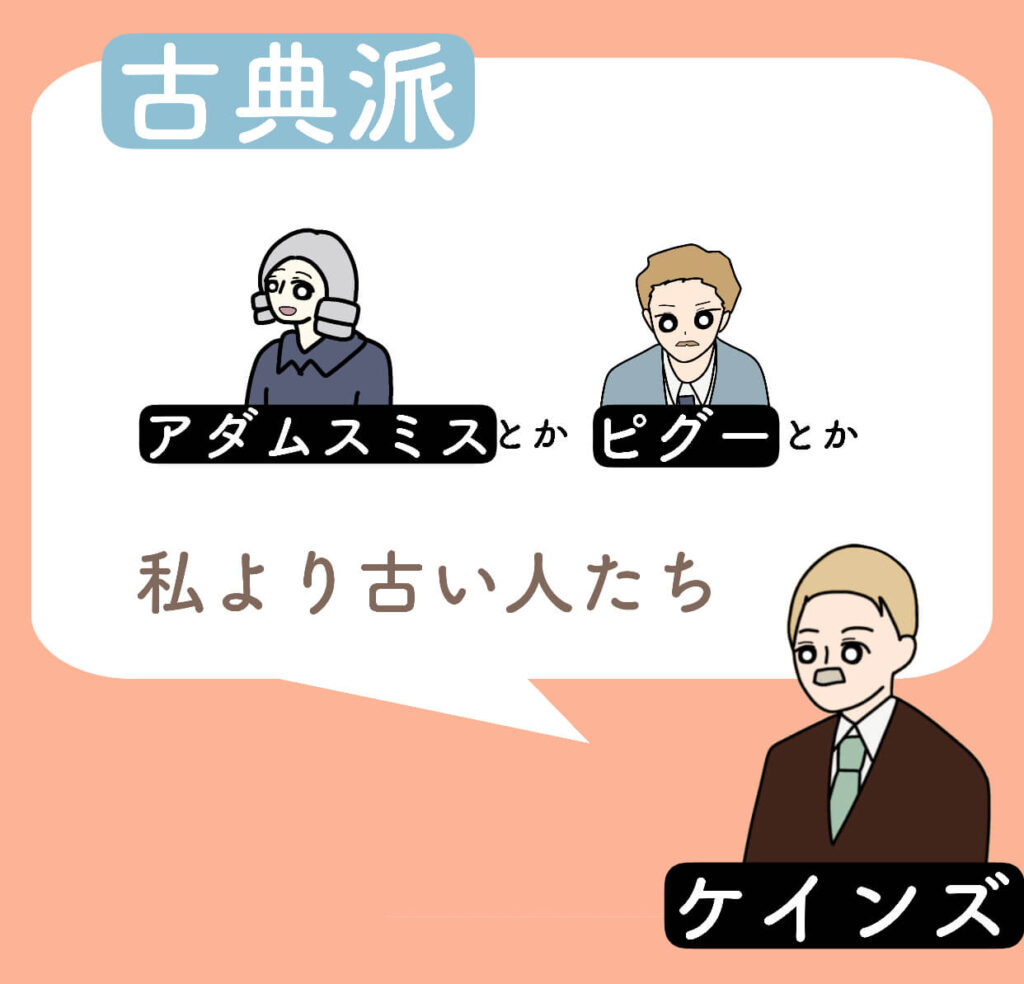
ケインズは、自分より前の人たちのことを「古い価値観を持った人たちだ」と考えました。
何が古いと思ったのでしょうか?
そのうちの一つは、投資と貯蓄に対する考え方です。
詳しくみていきます。
古典派の意見
まず「景気を良くするためには、設備投資が必要だ」と考えていたのは、古典派もケインズも同じです。
しかし、どのように設備投資を増やすべきかは、古典派とケインズで意見が分かれます。
古典派は、設備投資を増やすためには、お金が必要だから、とにかく貯金を増やさないといけない、と思っていました。
そのため、古典派は「貯金は素晴らしいことだ」と考えました。

貯金をすれば、銀行にお金が集まります。
そうすれば、銀行は、そのお金を他の人に貸すこともできます。
銀行にお金があるとき、銀行は誰かにお金を貸せるわけです。
だから、設備投資を増やすためには、銀行にお金を預ける人を増やす必要があります。
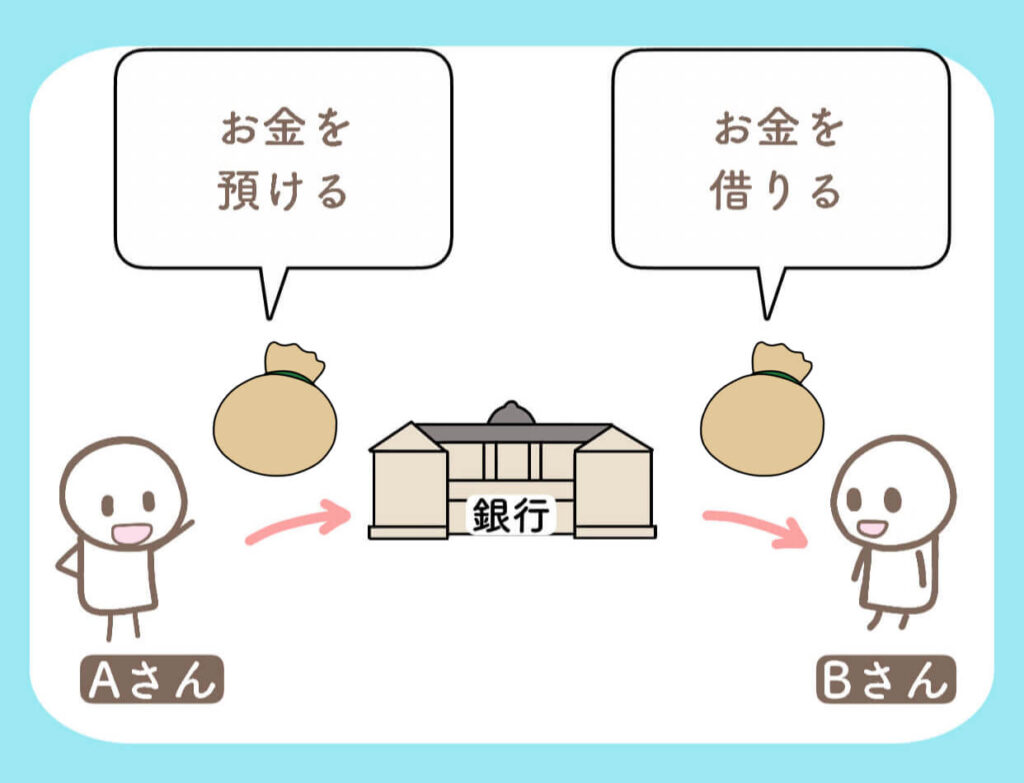
Aさんが銀行にお金を預けると、その分、銀行はBさんにお金を貸すことができます。
銀行から借りたお金を使って、Bさんは、設備投資をします。
貯金する人がいるから、設備投資をすることができるのです。
Aさんが貯金をすればするほど、Bさんは、たくさん設備投資ができます。
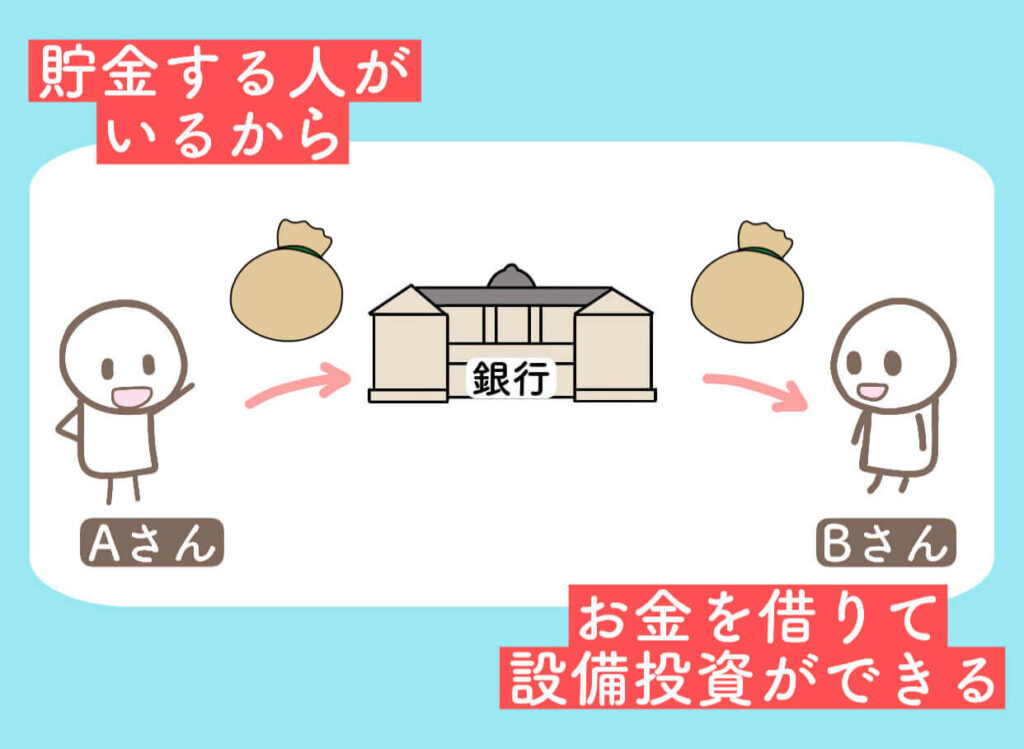
とはいえ、みんなが貯金しすぎてしまうと、よくありません。
買い物をするお客さんが減って、お店が儲からなくなってしまうからです。
つまり、経済が止まります。
そのため、貯金しすぎるのは良くないとも考えていました。
バランスが大事なのです。
そのバランスを取る役割を果たすのが、銀行の金利です。
銀行の金利が、投資と貯蓄のバランスを整えます。
古典派がイメージしてたのは、次のようなサイクルです。
たくさんの人がお金を銀行に預けると、銀行のお金の量が増えます。
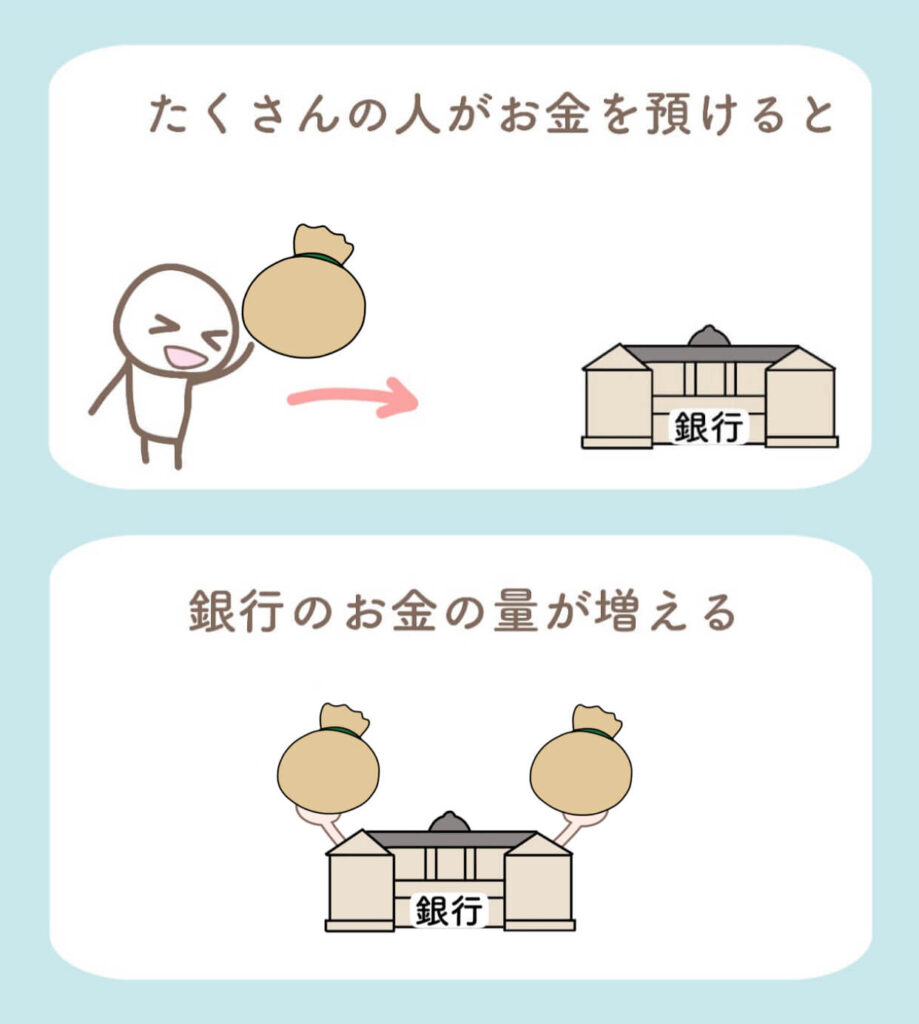
銀行のお金の量が多い時は、銀行はたくさんの人にお金を貸したいです。
そのため、銀行は、金利を下げます。
「金利が低くてもいいから、より多くの人に借りてほしい」と考えるからです。
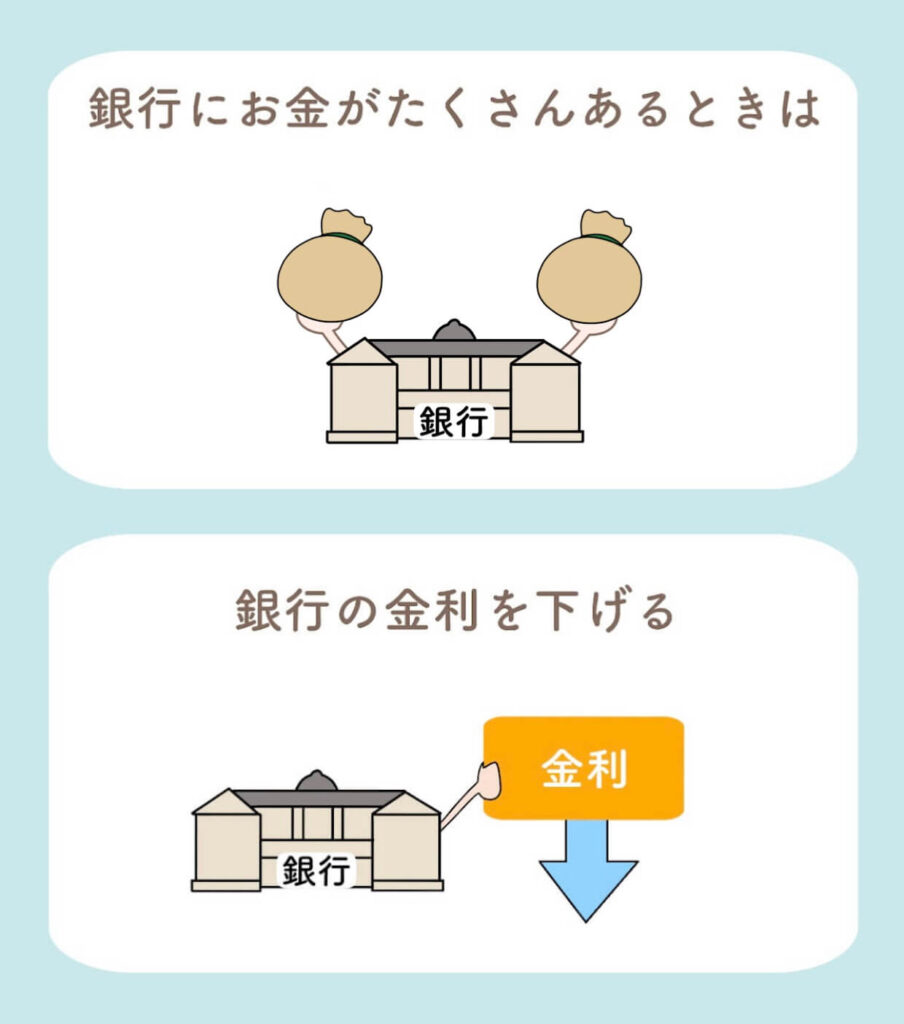
銀行の金利が下がると、企業は、お金を借りやすくなります。
すると、銀行からお金を借りる企業が増えます。

また、銀行の金利が低い時は、銀行にお金を預ける人が減ります。
銀行にお金を預けても、お金が増えないのです。
金利が低い時は、お金を銀行に預けておくメリットが小さくなるため、お金を預ける人が減ります。
貯金をしたがる人を増やすには、銀行の金利を上げることが大事だと古典派は主張しました。
金利が上がれば、みんながもっと貯金をするようになって、投資が増えると、古典派は考えました。
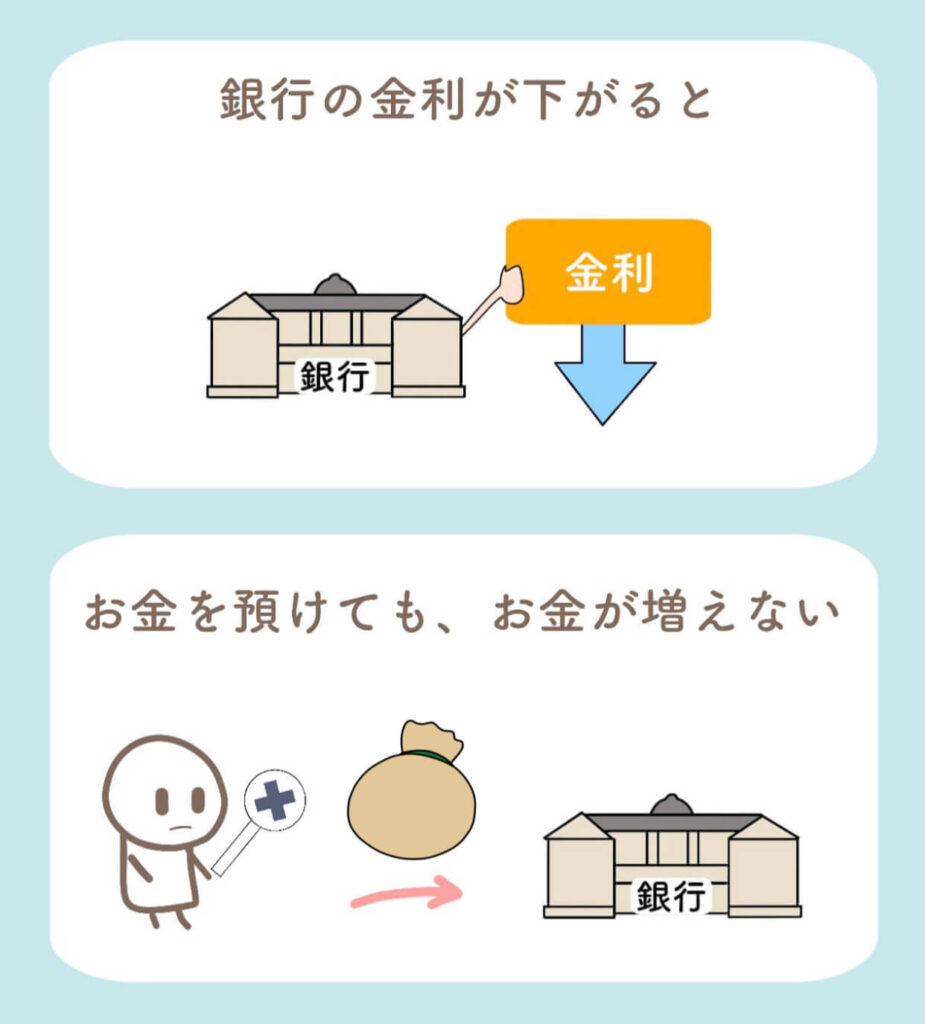
また、人は、いつかは買い物するつもりで、貯金してます。
貯金は、いづれ使われます。
人々が幸せになるためには、買い物をする必要があります。
買い物をしたくて、お金を持っているのです。
お金は、買い物するためにあります。
「貯金」が人生のゴールではないのです。
そのため、人生の中で、一時的に貯金することはあっても、いつかは買い物に使われます。
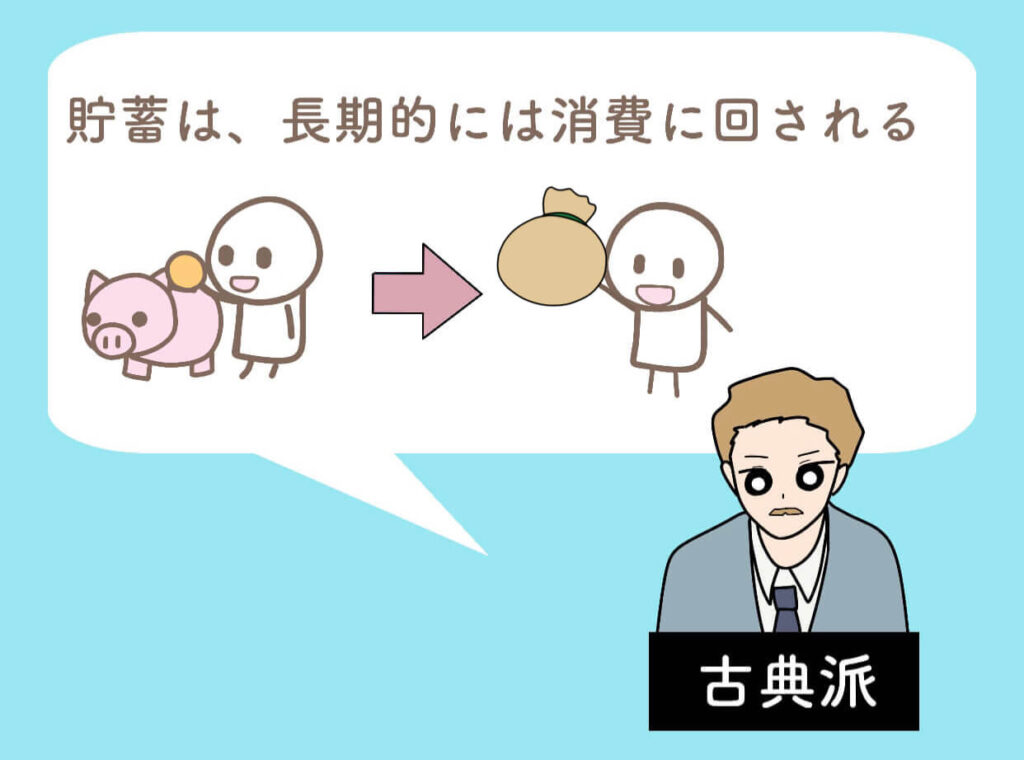
ケインズの意見
一方で、ケインズは、古典派の考え方に反対しました。
その理由は、貯金する人が増えると、お店が儲からなくなるからです。
例えば、お客さんがパンを買うのを我慢すると、パン屋が儲からなくなります。
Aさんが貯金をするというのは、いわば「今日は朝ごはんを食べない」という決断です。
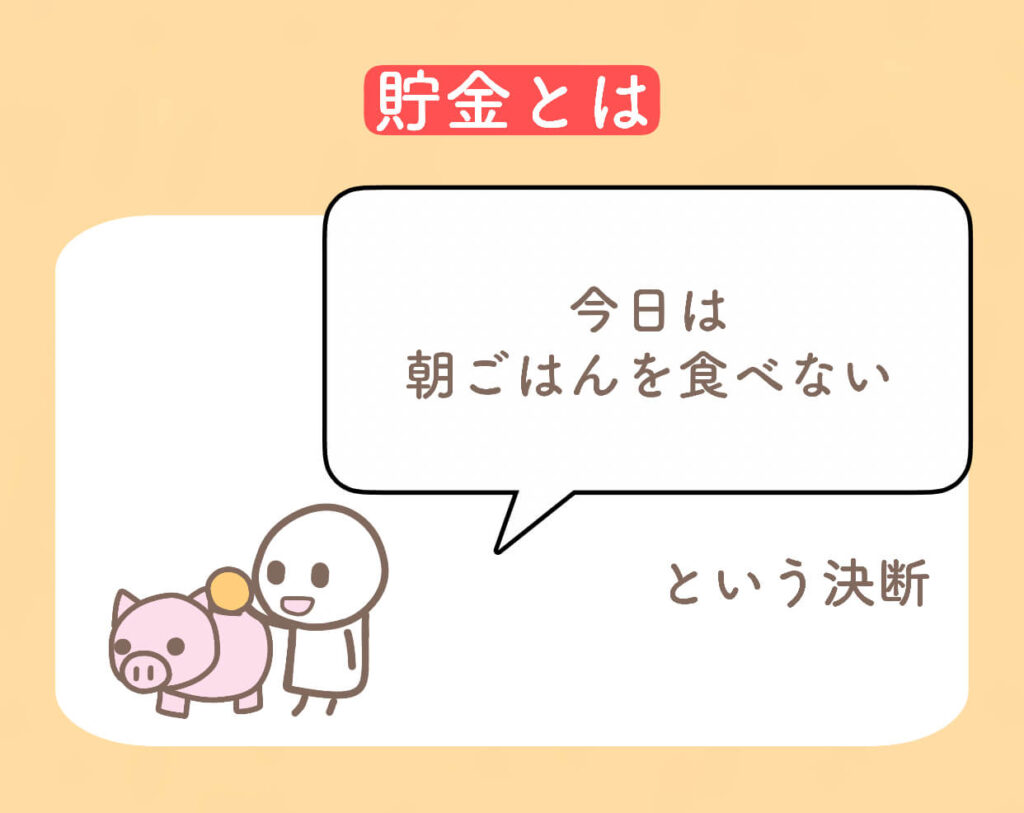
でも、そういう決断をしたからといって、別に来週は朝ごはんを食べるとか、1週間後か、1年後には贅沢する、とか約束するわけではありません。
今日、何も買わない代わり「いつか買い物をする」と決断しているわけではありません。
「今日は朝ごはんを食べない」という決断は、今日のパン屋さんが儲からなくなるだけです。
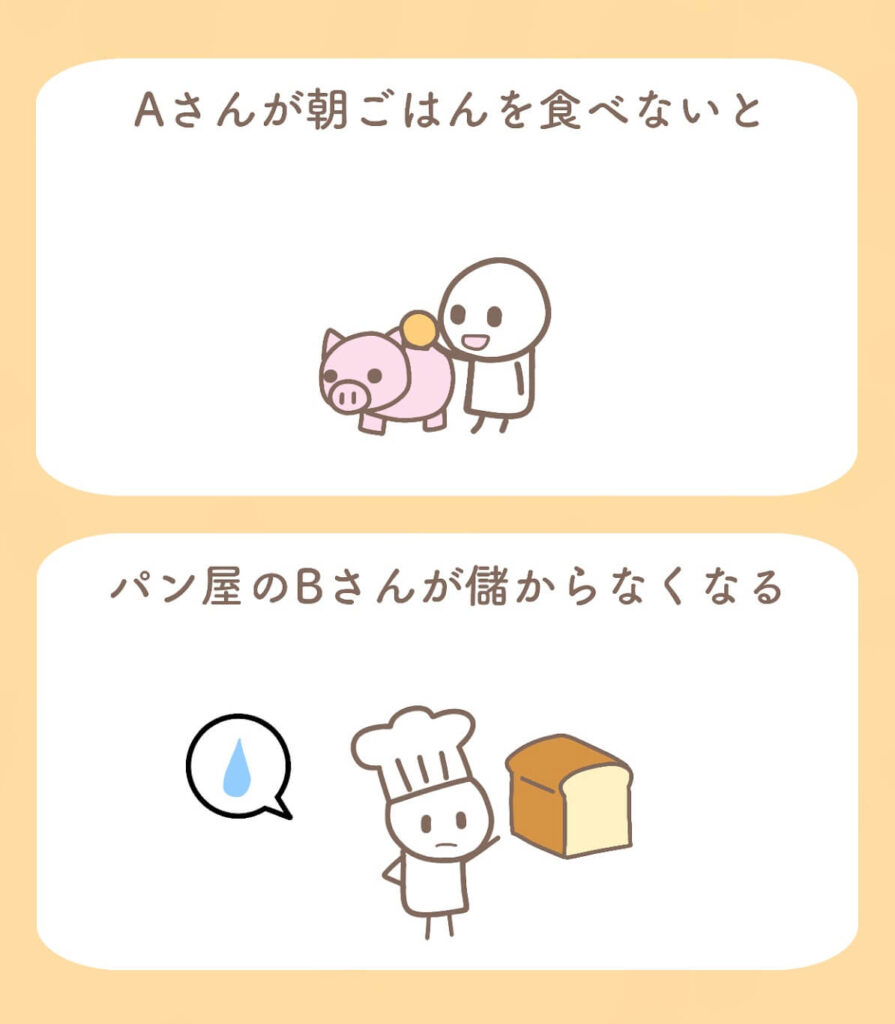
その分「未来で儲かるか?」と言われれば、そういうわけでもありません。
今、儲からなくなるだけです。
現在の需要が減るだけです。
今日の儲からない代わりに将来、儲かるようになる、というわけではないのです。

また、「今日は朝ごはんを食べないぞ」という決断して、本当にその人は、朝ごはんを食べなかったとします。
すると「あ、朝ごはんを食べなくても生きていける」と気付きます。
その人は、その後も、朝ごはんを食べるのをやめるかもしれません。
今、節約すると、将来も、節約するようになる可能性のほうが高いのです。
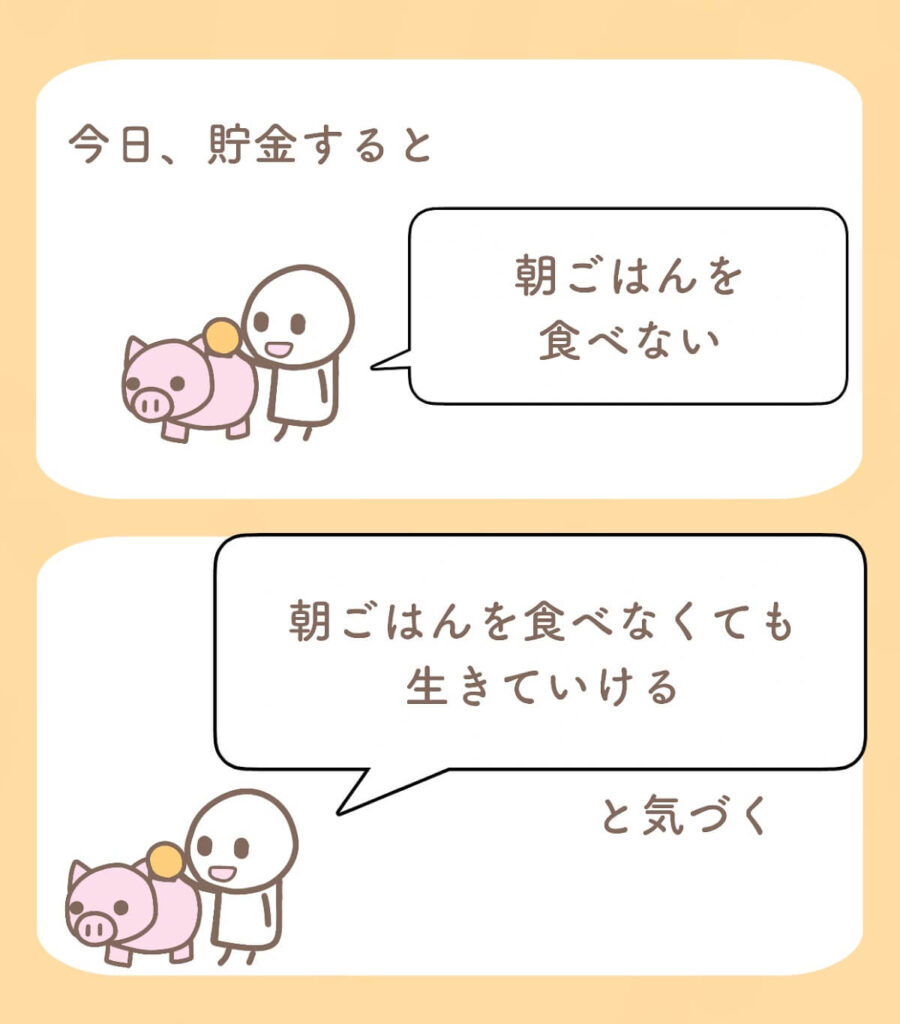
パンが儲からなくなれば、パン屋は「お店を大きくしよう」という気持ちになれなくなります。
設備投資も諦めるようになります。
こうして、設備投資の需要すら引き下げてしまうのです。
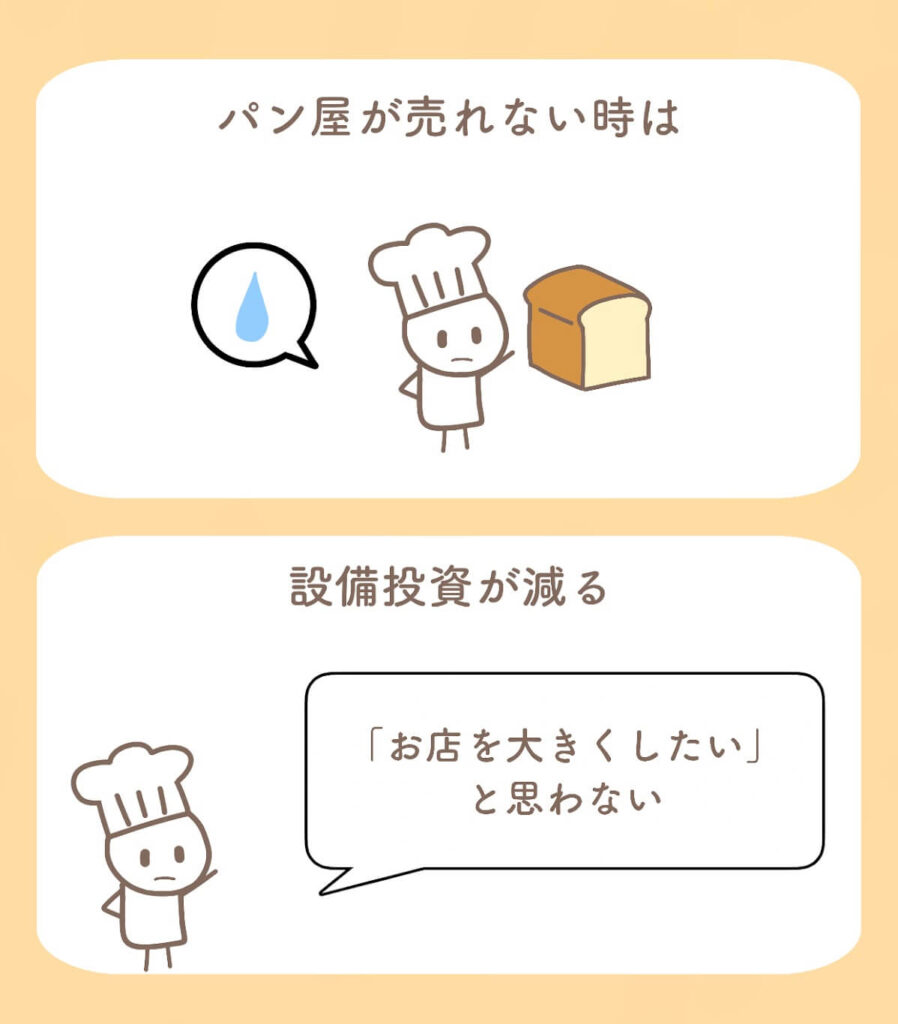
貯金は「今日、貯金する代わりに、明日、贅沢しよう」というものではありません。
「今日も貯金するし、明日も貯金しよう」と考えるのが普通です。
貯金した分、経済は止まります。
しかも、貯金は、貧富の格差を悪化させる原因にもなります。
貧乏な人はお金をすぐ使ってしまうけれど、お金持ちは使い切れないお金を貯金します。
貯金をした財産を、子どもに相続させたら、貧富の格差が次世代に受け継がれてしまいます。
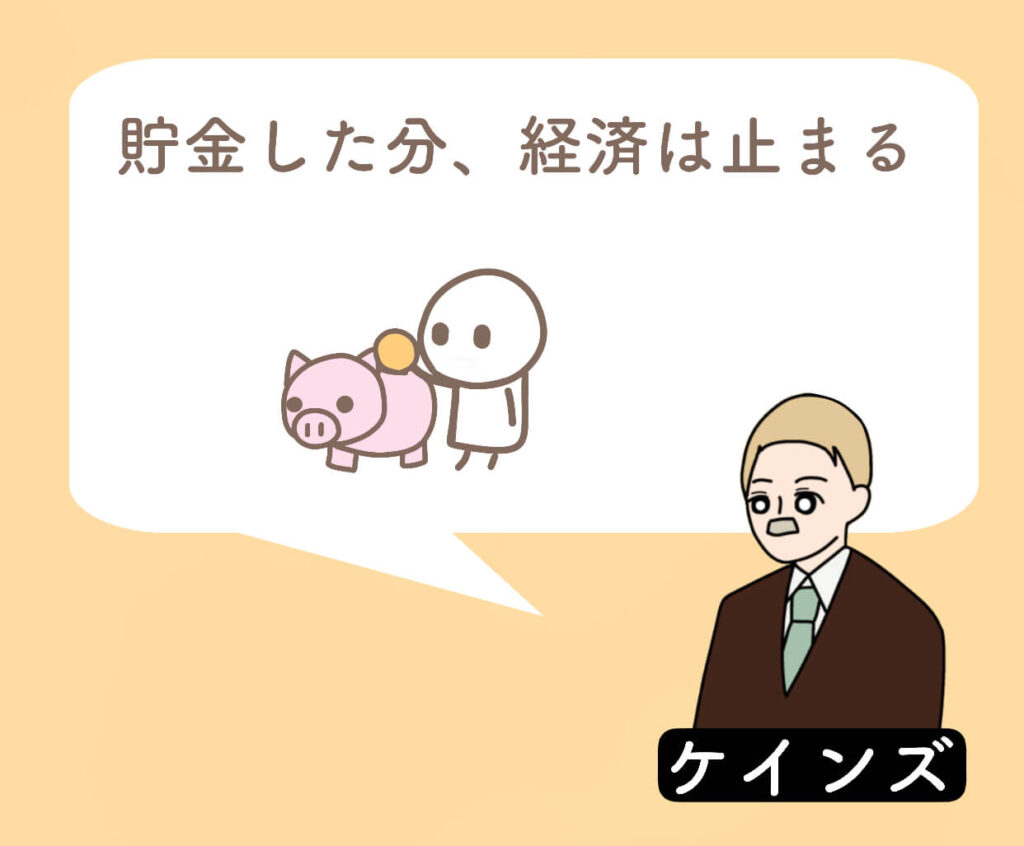
ケインズより前の人たちは「貯金は良いこと」と、考えてきました。
なぜなら、お金は買い物することにしか使えないからです。
人は買い物することで、幸せになります。
貯金をしても幸せになりません。
貯金したお金は、最初的には使われる、と考えられていたのです。
しかし、これは、間違っているとケインズはいいます。
ケインズにとって、貯金は、よくないことなのです。
貯金しても、設備投資が増えない理由
パン屋さんは、オーブンを買ったり、お店を大きくしたりします。
その理由は、売れる見込みがあるからです。
「もっとパンが売れそうだ」と思う時に、お店を大きくします。
パンをたくさん作った方が儲かる時は、パンをたくさん作るための設備を、お金をかけて準備します。
「将来、儲かる可能性」がある時に、設備投資をするのです。
しかし、人々が貯金をするとパンが売れなくなります。
「将来、儲かる可能性」は増えません。
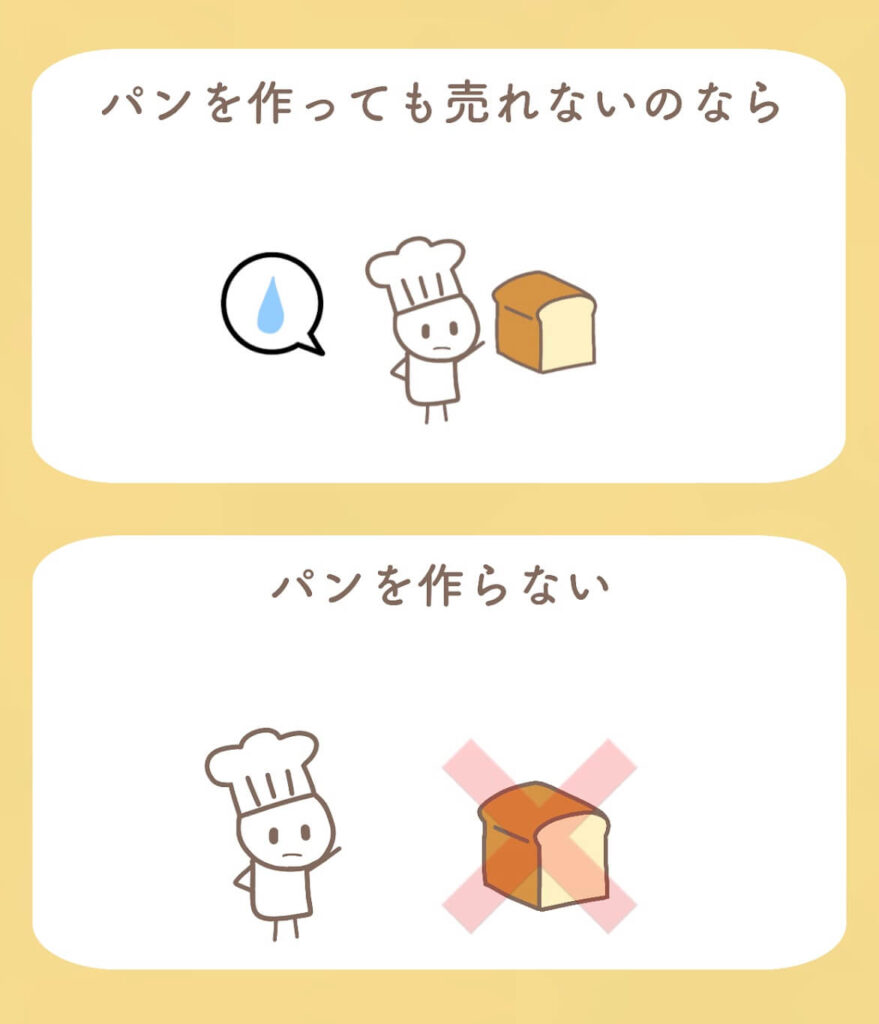
古典派は、「無駄な買い物をせずに、貯金しろ」と考えました。
しかし、無駄な買い物をせずに、貯金する人が増えると、パン屋が儲からなくなります。
人々がパンを買わない時は、パン屋は、パンを作る量を減らします。
パンを作っても売れないのなら、パンを作らない方がいいのです。
つまり、人々が貯金をしても、投資は増えないということです。

ケインズは、「みんなが貯金ばかりしてしまうと、ものが売れなくなってしまう。だから、設備投資もおこらない」と考えました。
つまり、貯金が多いからといって、かならず投資が増えるわけではない、というのがケインズの考え方なのです。