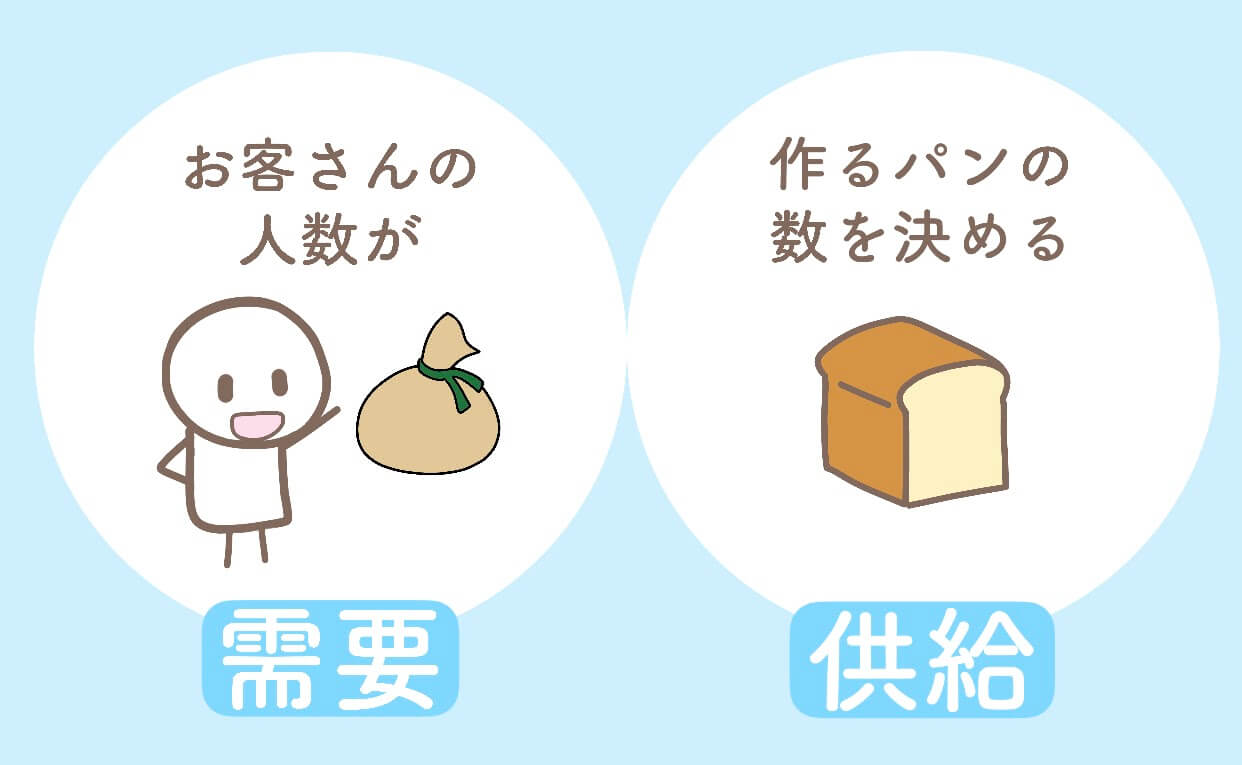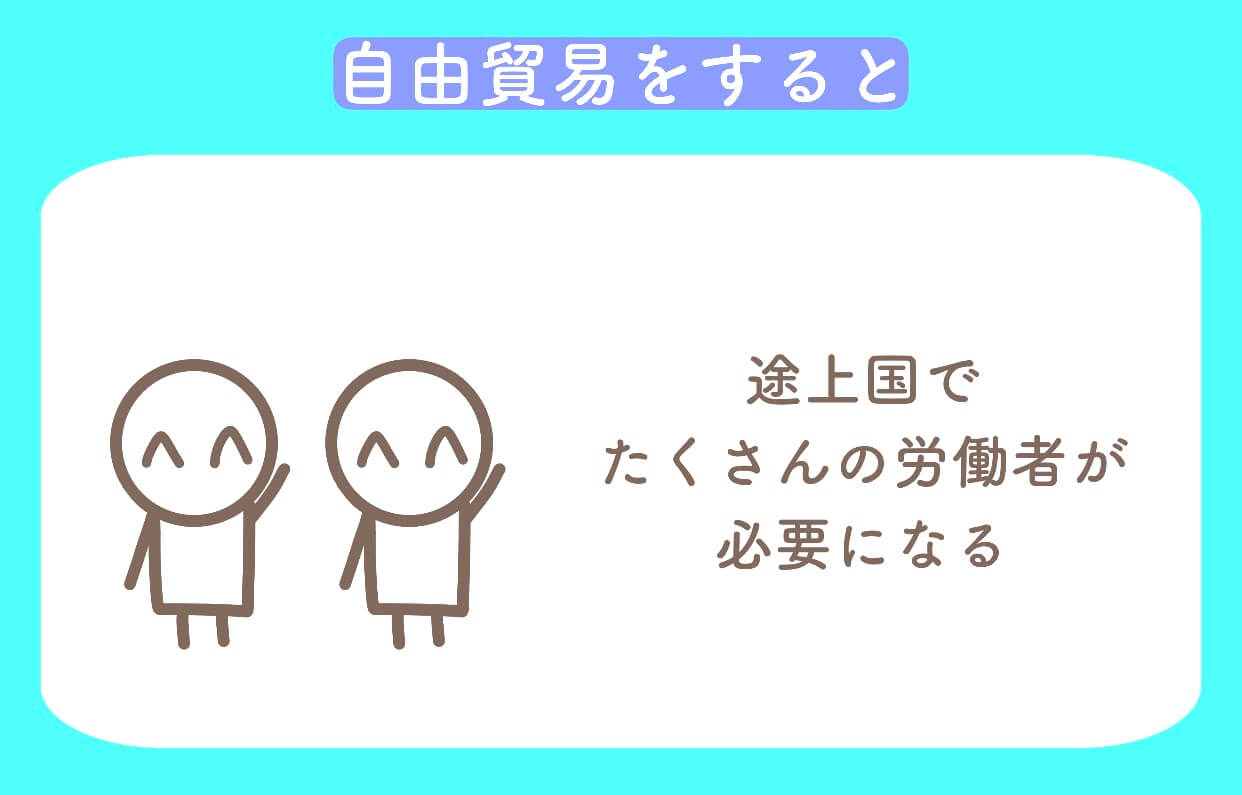私は、ソーシャルビジネスを謳う企業の取引先で3ヶ月インターンをしたため、現地で見たことを紹介します。
あくまでも、個人的な意見であることをご了承ください。
給食制度
私が働いたのは、バングラデシュの革製品工場です。
私が働いていた工場には、給食制度がありました。
給食制度とは、給料の一部をお金として渡すのではなく、給食として食べさせるという制度です。
この仕組みが始まった理由は、現地の労働者がご飯を食べないせいで、仕事中に倒れてしまうからだそうです。
現地の労働者たちは、給料をもらっても、自分のために使うのではなく、子どもたちに食べさせるために使ってしまうのだそうです。
そのため、労働者が栄養を取ってないことを心配した日本人が、職場で給食を食べさせる制度を作りました。
そうすることで、労働者がしっかり栄養を取るようにしてほしいと考えたのだそうです。
実態
しかし、実際には、給食に参加するのは、階級の高い人たちだけでした。
その工場で働く私の同僚(階級の低い人たち)は、お昼になると、家に帰って、お米に塩をかけて食べていました。
また、ニワトリが卵を産んだら、一つの茹で卵を3人で分けて食べる姿も見ました。
それほど、食べることに困っている労働者もいたのです。
その一方で、階級の高い人たちは、給食用にもらったお金を使って、パーティを開き、ジュースを飲み、交流の場にしていました。
また、そのメンバーだけでは、お金を使いきれないらしく、余った料理は、夕飯として、持ち帰るように言われました。
私も弁当を3つ渡されたことがあります。(食べきれなくて捨てました)
私は、毎回そのパーティに呼ばれる人の1人でしたが、「みんなのための給食費じゃないのか?」という疑問がつきまといました。
パーティに参加していた人に、なぜ全員が参加しないのか?と聞いたところ、全員が座るスペースがないからだと答えていました。
また、給食に呼ばれないメンバーに、給食についてどう思うか聞いたところ、「上」の人と、一緒に給食を食べるのは、文化的に難しいとのことでした。
給食に呼ばれないメンバーは「下」の階級だから、参加してはならないのだそうです。
考察
バングラデシュの上下関係は、日本と違います。
日本には、年功序列がありますが、バングラデシュでは、生まれた家庭(学歴)によって、上下関係が決まります。
日本人のように、みんなが同じ教育レベルというわけではないのです。
そんな国に日本人が「仲良く給食を作って食べてください」と言っても、無理だったようです。
考え直すべき点
私は、日本人が考えた当てずっぽうなアイデアを途上国に押し付けるのは、良くないと思います。
なぜなら、現地には現地の文化があるからです。
「日本人のやり方が正しくて、バングラデシュ人のやり方が間違ってる」と言う認識を持っていると、どこかで、欺かれるようになると思います。
私のインターン先では、給料の一部を、お金の形で渡すのではなく、給食として渡すというルールがありました。
その理由は「貧しい人は、お金を上手く使う判断力がないから」です。
労働者は、給料を自分のために使えずに、結局、子どものために使ってしまうからです。
強制的に給料を没収して、給食を食べさせようということです。
しかし、現地人の判断は、こちらが考えているより合理的です。
途上国の人は、日本人の「判断力」を求めてるわけではないと思うのです。
それに、給料は、彼らが働いて稼いだお金です。
それを日本人が勝手に「子どものために給料を使ってはいけない」と判断して良いのでしょうか?
たしかに、日本人側はバングラデシュ人たちのことを「ファミリー」と呼び「何でも話し合おう」と距離を縮める努力していましたが
バングラデシュの人にとって、日本人はただの「取引先」です。
つまり、お客さんです。
お客さんに、給料の使い方を指図されたくないし、何でも話し合うわけないのです。
反論を受けつけない日本の風潮
その職場で働く日本人は「何もしないよりは、お節介をしたい」という性格の人が多かったです。
そのせいで、そのお節介が本当に迷惑になっていることを説明しても、私が攻撃されてしまうだけでした。
さらには、現地の人に対して「頭のおかしい外国人」「早くクビになれ」などと日常的に罵ってくる日本人もいたため、現地の人は、日本人に「○すぞ」と言い返すほどでした。
日本人たちは「自分がヒーローであり、反論を言ってくる現地の人は倒すべき悪党である」と信じているようでした。
当時は私なりに、通訳(喧嘩の仲裁)を頑張りましたが、私自身も精神的に疲労したため、その職場からは離れることにしました。
学んだこと
途上国にいきなり飛び込む日本人は「何でも良いから何かを始めよう」と生き急ぎてる人が多いです。
そして、いったん何かプロジェクトが始まると、反論を言うこと自体が「悪」になってしまうのです。
また、ソーシャルビジネスで、現地の人たちに主体性を求めるのは難しいです。
なぜなら、現地の人が求めているのは「お客さん」であって「ヒーロー」ではないからです。
ソーシャルビジネスとは
ところで、ソーシャルビジネスと、普通のビジネスは何が違うのでしょうか?
そのソーシャルビジネスの企業は「現地に雇用を生み出している」から、ソーシャルビジネスであると謳っています。
しかし、普通のビジネスも現地に雇用を生み出しているはずです。
では、ソーシャルビジネスと普通のビジネスは何が違うのでしょうか?
たしかにソーシャルビジネスは、「結果」としては、普通ビジネスと、さほど変わりないのかもしれません。
しかし、ソーシャルビジネスとは、社会問題解決を「目的」とした事業です。
「結果」は同じでも「目的」は違うのです。
普通のビジネスと何が違うのかといえば、「心の持ち方」が違うのです。
ソーシャルビジネスの人たちは、普通のビジネスマンと違って「高い意識」を持って働いているようです。